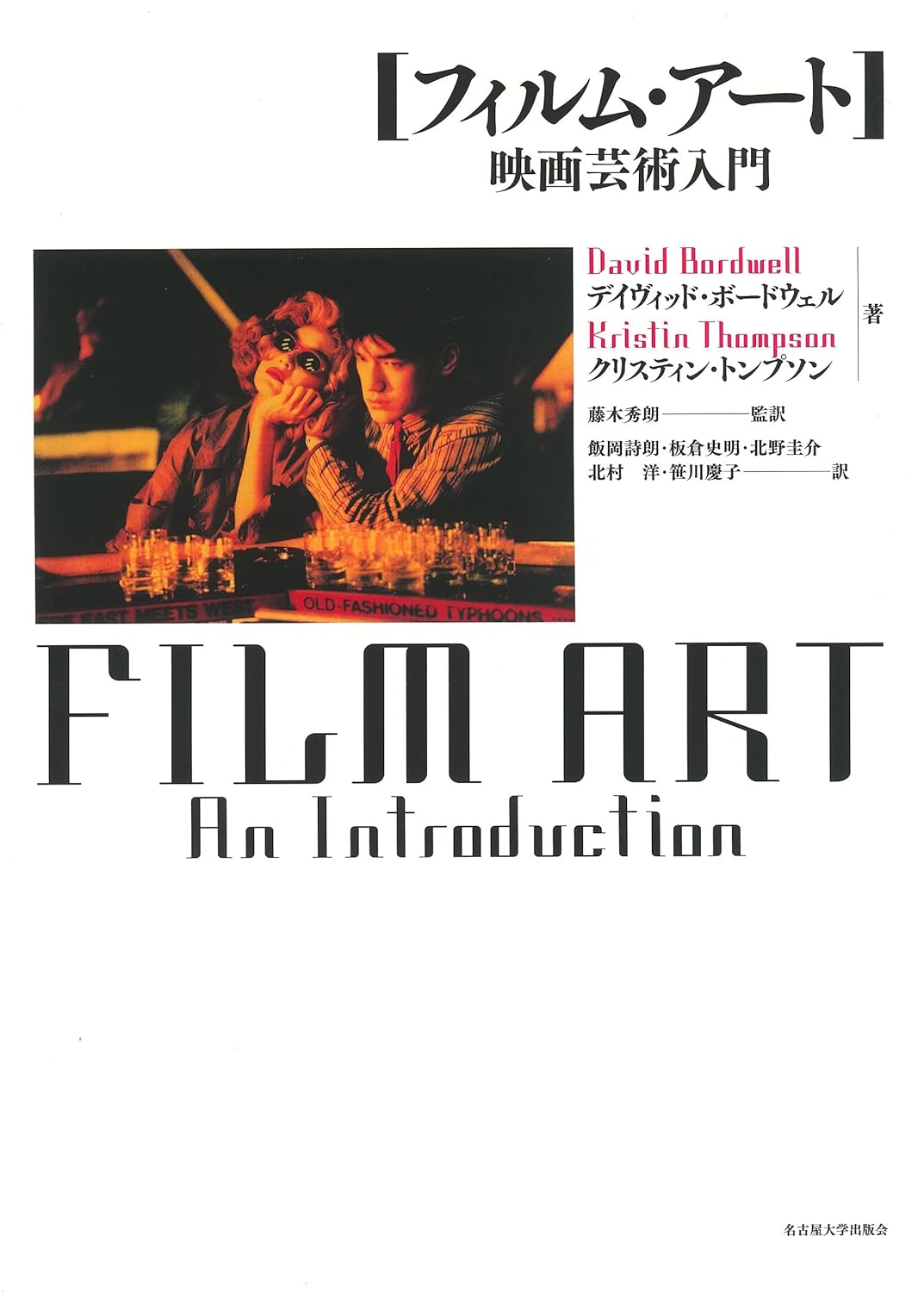フィルム・アート―映画芸術入門―
概要
映画に関連する事柄を体系的に網羅した概説書。映画機材の仕組みからジャンル区分、映画史から批評の書き方まで取り上げられています。内容はかなりボリューミーなので、一読で全てを消化しきるのは難しいかもしれません。
中核を為すのは形式とスタイルの解説です。
形式とは一つの映画作品がどのように構造化されているのかを指します。代表的なのはフィクション映画における物語形式ですね。
これに対してスタイルとは映画を構成する諸要素、すなわちミザンセンや撮影法、編集や音が作品内でどのように機能しているのかを指します。
映画とはこの形式とスタイルが互いに組み合わさってできている、というのが本書の主張です。
さらにドキュメンタリーや実験映画、アニメーションといったジャンルも扱っており、実写の物語映画にとどまらない広範な分野を見渡すことができます。
私が何言に良質だと思ったのは「付論3.映画とビデオ-画像はどこに行ったのか」という箇所です。ここではブラウン管テレビの時代に映画をテレビでオンエアすると、どのように映画が変形されてしまうのかが画像付きで解説されています。『シャイニング』のオープニングで、劇場公開時には見えなかったヘリコプターの影がビデオでは見えてしまったというエピソードはこれが原因です。ワイドテレビしか知らない私には非常に興味深い内容でした。
映画を観るとき観客は能動的に参加している
本書は第2章「映画形式の意味」において、映画を観るとき観客は能動的に参加していると主張します。
例えば物語映画の場合なら、映画のプロットがどのように展開するのかを観客は無意識に予測しているということです。「このキャラクターはどんな役割を果たすのか?」、「主人公は次にどんな行動を取るのか?」、「どのような結末を迎えるのか?」といった疑問の答えを探しており、映画が進むに従って予測をその都度修正していくのです。
これは映画に限らず、全ての芸術作品に当てはまると思いました。文学作品の場合でも、読者は物語の展開を予測しながら読みますよね。美術を鑑賞するときも「この絵は何を表現しようとしているのか?」、「描かれている人は誰で、何をしているのか?」といった疑問が頭に沸いてきます。さらに音楽を聴いているときも歌詞の意味を考えたりメロディーの展開を予測したりします。だからこそ鑑賞者に驚きや感動をもたらすことができるのです。こうした作品鑑賞はスポーツや創作などに比べて受動的だと見做されがちですが、実は能動的に思考しているんですね。
逆に映画を観ていて退屈だと感じるのは、作品が鑑賞者に能動的な参加を促せていないことが原因だとも考えられます。つまらない映画を観ているときは思考がストップしている、もしくは他の事に気を紛らわせてしまいますよね。これは作品の内容に関心を持てず、プロット展開の予測を放棄している状態だといえます。例えばミステリー映画なら「事件の犯人が誰であろうとどうでもいいな…」、恋愛映画なら「主役2人の恋愛が成就しようとしなかろうとどうだっていいな…」と感じてしまうことですね。映画の要素が観客の興味を繋ぎ留められず、100%受け身の状態にさせてしまっているのです。
私たちは古典的ハリウッド映画に囚われている
古典的ハリウッド映画とは、主に20世紀前半のハリウッドで制作された映画群を指します。ビリー・ワイルダーやアルフレッド・ヒッチコックはこの時期の監督です。主な特徴としては
・主人公に明確な目標が設定されている点
・物語に強い因果性が認められる点
・はっきりとした結末が用意されている点
などが挙げられます。古典的ハリウッド映画の影響力は大きく、こうした作品が外国へ大量に配給されたため、様々な国の映画製作者が参考にしていました。
私たちは映画と聞くと、どうしてもこれらの作風を映画のスタンダードだと考えてしまいがちです。しかしこれは数あるシステムの一つに過ぎず、古典的作風から逸脱した作品も当然生み出されています。本書ではその代表として『勝手にしやがれ』、『東京物語』、『恋する惑星』の3作品が第11章「映画批評―分析例」で重点的に考察されています。
例えば『東京物語』ではストーリーに直接関係しない場所のシーンが時折挟まれます。原節子演じる紀子が義母の危篤を電話で告げられるシーンの後、工事現場を写すショットが2つ挿入されています。この工事現場は物語には関係ありません。こうした無関係の場所を移したショットを度々挿入する理由として、ストーリー展開を少し先延ばしすることによって観客の期待をじらし、編集やミザンセンに注意を促すためだと本書では考察されています。映画本編の全てのシーンに物語上の意味があると私たちはつい思ってしまいますが、それは古典的ハリウッド映画という1スタイルの特徴に過ぎないことがわかります。
私はこの箇所を読んで『惑星ソラリス』を想起しました。この映画では前半に首都高を運転者目線で写した映像が延々と流されるシーンがあります。この場面もストーリーとはほとんど関係がありません。しかし高スピードで流れるようなこのPOVショットは観ていてとても心地がよい。タルコフスキー監督は純粋な視覚的快楽を追求するためにこのシーンを挿入したと考えられます。こうした映像の力がこの映画を魅力的にしているのは間違いないでしょう。
記述ミスが散見される
最後に気になった点を一つだけ述べておきます。それは記述のミスが散見されることです。
この書籍では映画の画像が多く掲載されているのですが、この中に『ジュラシック・パーク』の画像があります。しかし本書ではなぜかその続編である『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』だと紹介されています。しかも1か所だけでなく複数箇所にわたって。この他にも『エイリアン』の監督がジェームズ・キャメロンだと記載されていたり、黒澤明の『用心棒』を元にした西部劇を『夕陽のガンマン』だと紹介していたり。私が気が付いていないだけで、もっとたくさんあるのかもしれません。
これは原文でもそう記載されているのか、あるいは翻訳によるミスなのか?どちらにせよ映画に少しでも詳しい人ならすぐに気が付く初歩的な間違いなので、興ざめしてしまいましたね。とはいえ私が読んだのは初版なので、後の版では修正されているかもしれません。
まとめ
何しろ取り上げられてる題材が膨大なので、映画好きであれば得られるものは多いと思います。今回ご紹介した内容はほんの一部ですので、興味を持たれた方は読んでみてください。あの有名なイマジナリーラインについても図で解説されていますよ。
注意点を挙げるとすれば、作品のネタバレが多く含まれてることでしょうか。まあ映画を考察する書籍なので、内容に踏み込んでしまうのは致し方ないと思います。それと当たり前ですが、取り上げられる映画を観ていた方が解説を理解しやすいです。参照される映画作品も膨大なので全てをチェックすることは不可能ですが、『市民ケーン』と『北北西に進路を取れ』は観ておいた方がいいと思います。特に前者は著作権が切れており、無料で鑑賞することができるのでぜひ。

フィルム・アート―映画芸術入門―