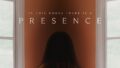目次
作品情報
ホロコーストを生き延びて渡米したユダヤ人建築家の物語。
監督は『シークレット・オブ・モンスター』のブラディ・コーベット。
主演は『戦場のピアニスト』のエイドリアン・ブロディ。共演は『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のフェリシティ・ジョーンズ、『メメント』のガイ・ピアース、『女王陛下のお気に入り』のジョー・アルウィン、『ニンフォマニアック』のステイシー・マーティン、『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』のラフィー・キャシディ、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』のアレッサンドロ・ニヴォラ。
IMAX上映館が少ない・・・
2025年3月現在、日本国内でIMAXシアターを導入している映画館は合わせて52館です。しかし『ブルータリスト』をIMAXで上映している映画館は、現時点でたったの16館に留まっています。
日本でのIMAX上映が報じられたのは1月24日、公開の約1か月前です。IMAXでの上映が決まった際には、すでにどの映画館に配給するのかが確定してしまっていたのでしょうか。
「そもそもIMAXで観るような映画なのか?」と思われるかもしれません。しかしこの作品には”IMAX映え”する要素が多く含まれています。
例えば自然の景観や建築物を雄大に写した多くのシーン。特に「第2章」で列車が脱線する場面やカッラーラの採石場を映した場面、建造中のヴァン・ビューレン コミュニティセンターを映した場面には、鑑賞者を圧倒させる美しいビジュアルに溢れています。
さらに音響への強いこだわりも感じられます。冒頭の「序曲」からサイレンのように音階が上昇し、金管楽器によるファンファーレが鳴り響く。ここで観客の意識を映画の世界へと一気に引きずりこみます。個人的にはIMAXの愉悦は大画面よりも、座席を震わせるほどの大音響にあると考えています。
私の住んでいる都道府県にもIMAXシアターはあるのですが、そこでは上映されていませんでした。映画自体が素晴らしい出来だっただけに、IMAXで観たかったという思いは強いです。近隣に上映館があるのなら、ぜひIMAXで観ることをおすすめします。
ペンシルべニアの理想と現実
第1章ではペンシルべニア州を讃えるニュース映像がたびたび挿入されています。曰く「ペンシルべニアでアメリカ合衆国を成立させた重要な会議が多く開催された場所であり、さらに一軒家が最も多い建立されていて自立を望む家族にとっては決断の地である」と。ペンシルべニアでは人々が繁栄を謳歌していることがアピールされています。
しかし実際はどうでしょうか。路上では貧乏人たちが炊き出しを求めて長蛇の列を作っています。これはヴァン・ビューレン家でのパーティーの場面で映し出される富裕層たちと対照をなしています。特にこれが顕著なのはラースロー(エイドリアン・ブロディ)がバスに乗っているシーンです。座っている乗客たちの持ち物は様々です。紙袋を掴んでいる人もいれば、高級カバンを持っている人もいます。吊革に掴まって立っているラースローはハンカチすら手づかみで握っており、最終的にそれを落としてしまいます。繁栄を謳歌しているのは一部の人々だけなのです。
一方でラースローがペンシルべニア(及びアメリカ)という土地にどこまで希望を抱いていたのかはわかりません。彼は随所で「僕は何にも期待していない」と発言しているのです。とはいえ自分自身にそれを言い聞かせているようにも見えます。
”ユダヤ人”と”ブルータリスト”という二重のアイデンティティ
ナチス政権がユダヤ人絶滅政策を行っていたことは周知の事実です。しかしそれだけでなく前衛的な芸術作品を「退廃芸術」として徹底弾圧していた歴史もあります。
ハリソン(ガイ・ピアース)から過去に作った建築の写真を渡された際、ラースローは「私と同僚は第三帝国から”非ドイツ的”だと拒絶された」と嘆いていました。つまり彼は”ユダヤ人”と”前衛芸術家”という2つのアイデンティティにおいて、ナチス政権の差別対象だったのです。
こうした偏見・無理解は戦後のアメリカにおいても根強く残っていました。例えばラースローが公の場で礼拝堂の案をプレゼンした際、彼の出自について厳しい意見があったことが述べられています。さらに着工後も、ユダヤ人ではなくプロテスタントの建築家を雇った方が良いのではないか、という意見が出されています。最終的にラースローは「俺たちユダヤ人は歓迎されていない」と絶望します。
ブルータリズム建築においても同様です。彼がアティラ(アレッサンドロ・ニヴォラ)の家具店で椅子を作成した際、彼の妻であるオードリー(エマ・レアード)からは「まるで三輪車みたい」と言われてしまいます。さらに礼拝堂の模型を披露した際、レスリー(ジョナサン・ハイド)からは「コンクリートを使うなんて無機質すぎる」と難色を示され、ジム・シンプソンからは「この建築作業で最も不要なのはコイツだ!」と非難されています。ラースローがハリソンを信用してしまったのも、自分の建築を初めて認めてもらえたことに感激したからでしょう。
アメリカは「自由の国」とよく呼ばれていましたが、その実態がこの有様です。冒頭のエルジェーベト(フェリシティー・ジョーンズ)の手紙では「偽りの自由が最も人を隷属させる」というゲーテの格言が紹介されていましたが、その後に自由の女神が映し出されるのは何とも示唆的です。
こうした状況下でもアメリカ社会へと巧みに溶け込んでいるユダヤ人は存在します。ラースローの従兄であるアティラ、エルジェーベトとジョーフィア(ラフィー・キャシディ)の入国を手助けした弁護士夫婦がその典型です。しかしラースローとエルジェーベトは最終的に「この土地は腐っている」としてアメリカを立ち去ることを決断します。彼らは新天地アメリカに敗れたのです。
ハリソン・ヴァン・ビューレンとは何者か?
ハリソンはラースローをレイプするとき「お前たちユダヤ人は社会に寄生している」と罵っています。彼は自身の資産を目当てにすり寄ってくる人々を心底軽蔑しているようです。それは「援助を求めてきた”母の両親”にサイン無しの小切手を渡してやった」というエピソードからも読み取れます。
ラースロー自身もこうしたユダヤ人に対するレッテルを気にしており、修道女からミサへの協力を求められた際も「故国の人々に物乞いだと思われるのはごめんだ」と発言しています。
しかし実際に寄生・搾取しているのは果たして誰でしょうか。ハリソンの息子であるハリー(ジョー・アルウィン)は自分で父の書斎の改装を注文したにも関わらず、父親に怒られた結果「料金は払わない」と言い出します。またハリソンがラースローに礼拝堂の建造を注文してハリーも彼を説得しますが、着工が始まった後は「みんな君に耐えている」と文句を言い始め、列車事故が起きた際はあっという間に彼を切り捨てます。しかし保険金が下りて建造が再開されるとまた彼を呼び戻すのです。あまりにも都合よく利用しすぎでしょう。
そもそもハリソンがラースローを見出したのも彼の建築に感銘を受けたからではなく、単に自分の書斎が新聞で称賛されたからなのではないでしょうか。列車事故が発生した際もやたらと自分の体面を気にしていました。彼にとっては自分の名声こそが何より大事なのです。エルジェーベトはそんな彼の浅はかさを見透かしていました。「(礼拝堂建築なんて)彼にとっては台所の改装と変わらない」と。
ハリソンの末路は劇中では明確に描写されていませんが、彼はあの礼拝堂で自殺したのだと思われます。彼は自身がレイプ犯かつ男色家であることを子供たちや関係者の前で暴露されています。これでは面子が丸つぶれです。この屈辱に彼は耐えられなかったのでしょう。
オープン・エンディングの「エピローグ」
映画のエピローグである「第1回建築ビエンナーレ」は映画全体の中で異彩を放っています。この部分をどう解釈したら良いのでしょうか。
ジョーフィアのスピーチの中でマーガレット・ヴァン・ビューレン コミュニティセンターが紹介されます。その内容によると、この礼拝堂が完成したのは1973年であり、それまで作業は中断していたことが伝えられます。ちなみに第2章の舞台設定は1953~60年です。
これらの情報から推測すると、ラースローとエルジェーベトは第2章での出来事の後にイスラエルに移住したが、エルジェーベトが死亡したのでラースローだけが73年にアメリカへ戻って礼拝堂を完成させた、と推測できます。さらに「アメリカでの最初の傑作であるこの礼拝堂は・・・」と述べられていることから、礼拝堂が完成した後もアメリカで活動し続けたことが伺えます。あれだけ忌み嫌った土地に彼は舞い戻ってきたのです。
ジョーフィアのスピーチはある言葉で締めくくられます。「大事なのは過程ではなく結果なのだ」と。そして映画冒頭での彼女が映し出され、物語は幕を閉じます。このラストシーンではまさに結果(スピーチを終えた1980年でのジョーフィア)と過程(ソ連兵に尋問されている1947年でのジョーフィア)が表現されています。
ではラースローの”結果”は彼にとって望ましいものだったのでしょうか?
彼はアメリカに戻って礼拝堂を完成させました。この礼拝堂自体はキリスト教徒のためであり、ユダヤ教徒の彼にとってはやや不本意なものではあったかもしれません。しかし強制収容所の閉鎖感を再現したり、自身と妻の繋がりを表現したりなど、礼拝堂建築に自分の芸術的エッセンスを注ぎ込んでいました。そうした作品がこのビエンナーレで評価されているのを見ると、彼の”結果”は成功といえるかもしれません。
しかしその一方でビエンナーレのパネルでラースローは「過去の人」と紹介されています。実際にブルータリズムは70年代終盤に衰退しているのです。エピローグで流れている電子音楽のような劇伴はこれまでの映画の雰囲気とは相容れないものであり、ラースローの時代は過ぎ去ってしまったようにも感じられます。
結局彼の建築は「恐ろしい言論が世を支配したときに政治的刺激を与えるもの」となったのか否か?そのどちらとも取れる表現となっています。解釈は鑑賞者に委ねられているのではないでしょうか。
まとめ
”アメリカで翻弄されるユダヤ人建築家”という骨子の他にも”ホロコーストが犠牲者に残した後遺症”、”ラースローとエルジェーベトの夫婦愛”、”ヴァン・ビューレン一家の俗物性”など多様な要素が散りばめられており、3時間半という長さを全く感じさせない面白さに満ちていました。観るたびに深堀りできる作品だと感じます。
また今作では15分のインターミッションが設けられています。最近は『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』といい『オッペンハイマー』といい長尺の作品が増えているような気がしますが、どちらも途中休憩は設けられていませんでした。3時間を超える長丁場だとトイレが心配になるし、鑑賞のハードルが上がってしまいます。インターミッションという文化、無くなってほしくないですね。
関連作品紹介:『ポップスター』(2018)
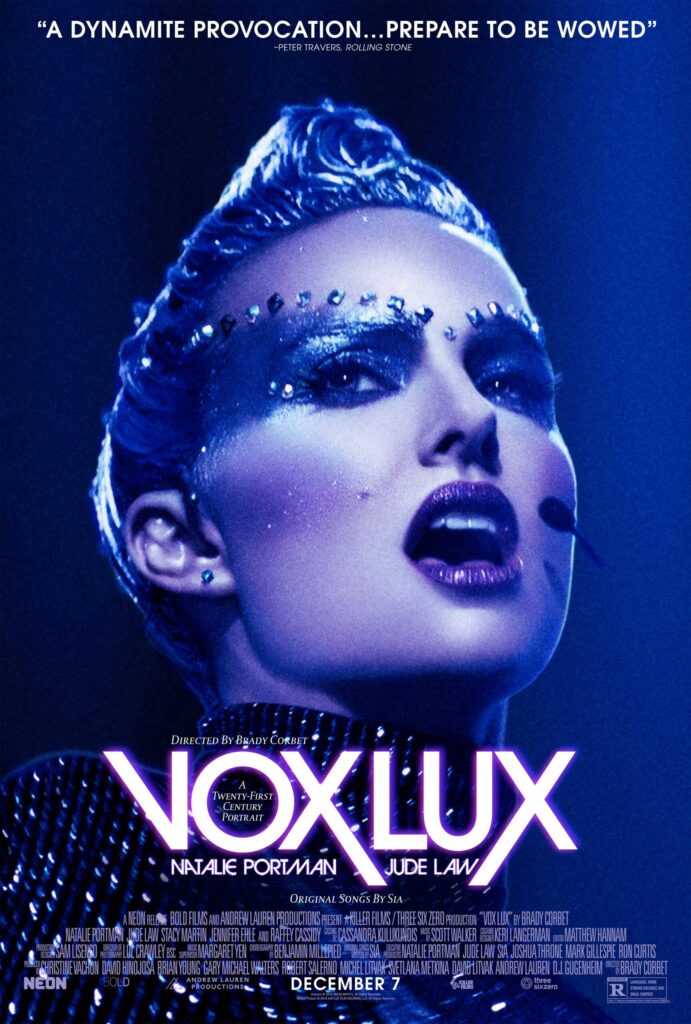
ブラディ・コーベット監督の前作。主演は『アナイアレイション‐全滅領域‐』のナタリー・ポートマン、『グランド・ブダペスト・ホテル』のジュード・ロウ。ステイシー・マーティンとラフィー・キャシディは今作にも出演しています。
主人公のセレステ(ラフィー・キャシディ)が通う学校で銃乱射事件が発生。彼女は撃たれながらも一命を取り留めます。音楽が趣味の彼女は歌を作曲して犠牲者の追悼式典でそれを披露したところ、結果は絶賛の嵐。彼女は一躍スターダムへの階段を昇り始めますが・・・。
銃乱射という大量虐殺をきっかけとして音楽の才能を開花させてゆくセレステ。しかしそれは彼女にとって本当に良かったことなのでしょうか?映画が進んでいくにつれて、こんな疑問が頭をもたげていくことになります。本作では前半と後半では大胆な時間の隔たりがあるのですが、その間の彼女に一体何があったのかが徐々に察せられる仕組みとなっており、描かないことによってドラマに深みが生じています。
また劇中でセレステが歌う楽曲はシンガーソングライターのシーアが作曲しており、その音楽性も見所です。作品のクライマックスはセレステのライブパフォーマンスとなっているのですが、ここで映画は最高潮に達します。特にラストで歌われる「EKG」という曲は歌詞がストーリーと密接に関連しており、サウンドトラックの中でも群を抜いた出来栄えです。
ナレーションが説明的すぎるという欠点はあるものの、独自の魅力を持った異色作です。

ポップスター(字幕版)